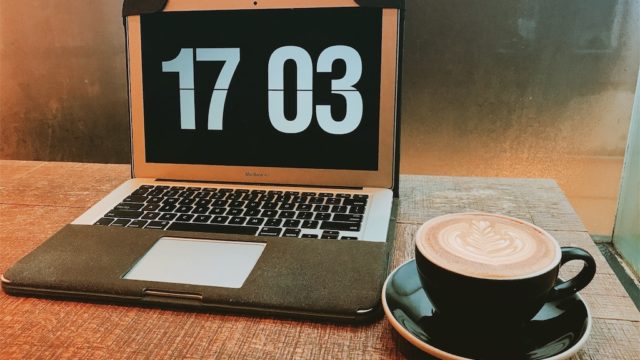コロナの影響で最近は家にいることが多い。
せっかくの機会なので課題図書である「レンマ学」を読んでいる。
しかし、内容が難しく理解ができない。読み進められない。
毎日読んでいてもなかなか理解できず、1週間くらい読んでも1章しか進まない。そのうちに本を開くのも避けるようになってしまった。
そんな時に以下の記事が偶然目に入った。
松岡正剛が語る「多読」の極意──多読ジム第二回工冊會
私は松岡正剛さんのイシス編集学校にお世話になっていたこともあったため、松岡さんがどのように本を読んでいるのか気になった。
「本を読む」ことに関して、松岡正剛さんほどの先達はいないだろう。
松岡正剛さんの著書「多読術」を手に取った。
「きっと多くの人が読書で気になるのは、「どうもアタマに入らない」ということですよね。それでついついあきらめたり、うんざりしたり、自分にがっかりしてしまう。そういうような気がするということでしょうが、これはね、ついつい全力で読もうとしすぎるからです。」
「しかし、本というのは著者が書いているわけで、その思想や書き方や言葉づかいには、われわれ読み手が持っている受容能力だけでは処理できないものは、いくらでもあります。」
言われてみれば、著者の言っていることを「理解する」というのもおかしな話だ。本ができあがるまでには著者の数十年分の人生があり、研究してきた期間がある。著者の人生という背景があって本が出来上がっているのに、それをたかだか2時間くらいで全て理解しようとしても無理な話だ。
本の内容を理解する。
どうしてそれが当然のことと思うようになったのだろうか。おそらく中高時代の国語の教育にひとつの原因があると思う。
現代文の授業では、あたかも筆者の意図が正確に理解できるのが当然かのように問題を出してくる。
「棒線部分の筆者の主張を15文字以内で述べよ」
小説の場合は
「棒線部分の主人公の感情はどのようなものだったか。以下の4つの選択肢から選べ」
など。
筆者の意見は明確で、内容の理解は当然と思ってきた。
しかしどうもそうはいかないようだ。
筆者の主張を100%理解できるわけではないとしたら、読むとはどういうことなのだろう。再び「多読術」に戻る。
「読書というのは、書いてあることと、自分が感じることが「まざる」ということなんです。」
「ということは、読書は著者が書いたことを理解するためだけにあるのではなく、一種のコラボレーションなんです。僕がよく使っている編集工学の用語でいえば、読書は「自己編集」であって、かつ「相互編集」なのです。」
少し難しいかもしれないが、簡単に言うと読書はもっと自由であっていいということだと思う。筆者の意見を理解するだけではなく、読んでいて自分が「おっ」と思ったところ、「モヤモヤ」したところ。
そのような感情が引っ掛かったところがポイントだ。
そして読む時のコツとして、本をノートとして書き込むことが提唱されている。気になる部分に線を引いたり、思いついたことを書き込んだり。形式は自由で構わない。自分の琴線に少しでも触れたものを、そこに記録していく。そして、そこが「あなたにとって」大事な部分になる。
ちなみに電子書籍だとマーカーは引けても、書き込むことができないから困る。
「多読術」を読んでから、無理に理解しようとはせずに、気になる部分をマーカーしながら読み進めるようになった。そうすると本を最後まで読み切ることができた。なおかつ自分が気になったポイントだけ見返してみると、一冊のほん全てが自分にとって気になるわけではないのだなと判明した。
以前、本はひとつのフレーズに出会えれば良い、という話を聞いたことがある。
私は本を読むときに「最初から全部読んで、理解しなくては」と思っていた。
しかし、「全部読まなくても良い」「気になったところだけ読んでもいい」というふうに考えるようになってからは、本を読むハードルがグッと下がった。
今晩はを改めて「レンマ学」手に取ってみようと思う。