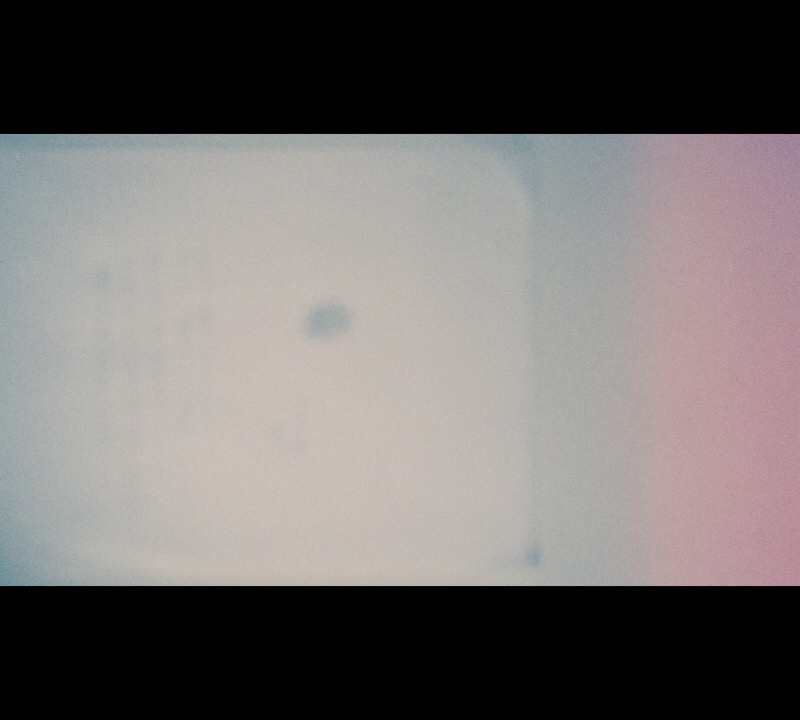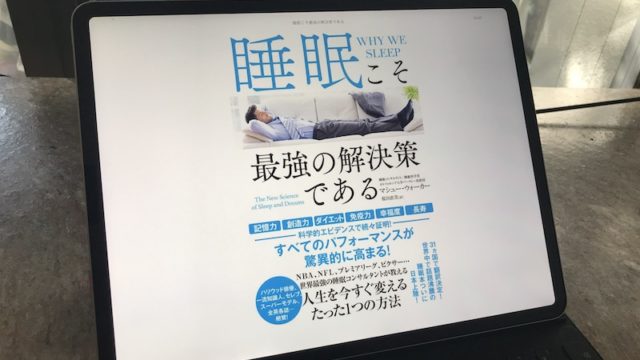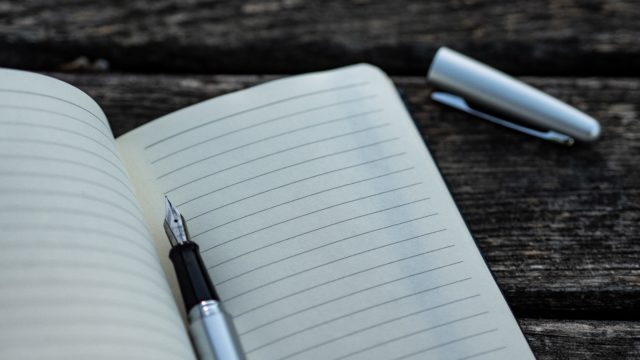こんにちは。しんいちです。
今日は安田登さんの「すごい論語」を読んでいました。釈徹宗さんとの対談の中で、「お葬式」の大切さについての話が出てきます。
その一方で先日、以下のようなニュースを見ました。
死ぬときはあえて「葬儀も墓もいらない」という人が急増中のワケ
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190707-00059211-gendaibiz-life
もともと大事にされていたお葬式が簡素化されつつある。これは一体どういうことなのでしょうか?
お葬式を非常に重要視する儒教
「すごい論語」の中では、儒教においてお葬式が非常に大事だったことが言及されています。
その例として2本の映画が挙げられていました。
1つは「菊豆」という中国の映画です。お葬式を執り行った後に、いざ出棺となると子供と奥さんが出棺を止めようとする。しかし出棺役の人はそれを払いのけたり蹴ったりするのに、それでもくらいつく。出棺を止めないと親不孝ものとされてしまうわけです。
また、韓国の「祝祭」という、映画では主人公の母の葬儀に際して、主人公が奥さんに貯金を降ろすように言います。いくら降ろすのか?と奥さんに聞かれると、「全部おろせ。金はこう言うときのためにあるんだ」と。
これは極端な例かもしれませんが、かなり激しいですよね。貯金を全部おろして葬儀をしたり、蹴られながらも出棺を止めたり。
個人的にはそこまでするのか?!というのが正直なところです。自分が死んだとしたら、お葬式なしで、もうお墓とかもいらないかな、と思っています。
そう思っているのは私だけではないようです。
死ぬときに儀礼はいらない現代人の増加
死ぬときはあえて「葬儀も墓もいらない」という人が急増中のワケ
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190707-00059211-gendaibiz-life
宗教学者の山折哲雄氏(87歳)は「葬儀も、墓も不要だと思っています。お骨も残さない『三無主義』」を提唱している。
また、宗教学者・島田裕巳氏は『0葬――あっさり死ぬ』という本を書いている。お墓がないことで、むしろ「千の風になって」という歌のように、どこにでも故人を感じることができると書いてあります。
また金銭的な理由もあるという。平均的なお葬式の予算は190万ほどだといいます。
金銭的な負担が軽くなることからも、あまりお葬式等にお金を使わない人が増えているそうです。
死者を排除するっていうより、後世の人の重荷になりたくない。それよりも子供の代に、お墓参りしてほしいとかない。
どうしてそう思うのだろうか?霊的なものを信じていないつもりはない。でも自分が幽霊になるという実感もないです。
死者の儀礼は土地に依存している気がする。インターネットが社会を分断した今、むしろインターネット上に埋葬してもらった方がいい「?」
情報が残る。誰かが思い出す、という機能はインターネット、特にSNSに、取って代わられたのではないだろうか。
土地や記憶の件はもうすこし考えたいと思います。