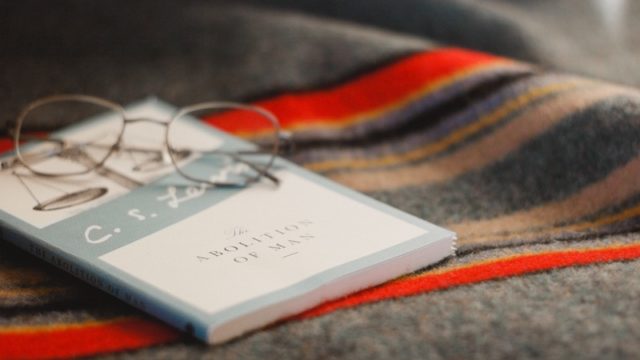こんにちは。しんいちです。
今日は仕事の記事がうまく書けずに、もやもやしていたので、本屋さんに文章の書き方の本を探しに行くきました。本屋さんで「誰でもすぐにかける文章の書き方!」のような本を見ていてもどうしても腑に落ちません。仕方ないので、本屋さんの他の書棚をふらふらと見回っているうちに、気づいたことがあります。それは、自分が読者として読みたいかどうかが大切である、ということです。
自分が読みやすくて、最後まで読みたくなるような文章。
そう考えるとシンプルなデザインの記事がいいと気がつきました。
今回の体験から、本で答えを探そうとするよりも、自分の頭でまずいろいろ考えてみることの大切さを感じました。
目次
- なぜ本をすぐに探してしまうのか
- なぜ本をすぐに探すと違和感があるのか
- 答えを出さないで考えてみる
なぜ本をすぐに探してしまうのか
最初に私が疑問にぶち当たってすぐに本屋さんにいって、「文章の書き方」という本を探した、その背景を考えてみたいと思います。
私は本の中に「答え」があると考えていました。技術的な本を読めば、自分の直面した課題に単純明快な答えをだしてくれると期待していました。
調べれば答えが出てくると思った背景はなんでしょうか。それはインターネットありきで育った世代だからだと思います。中学生の時にはiPhoneが発売されました。ケータイやインターネットの普及を身近に感じてきた世代の私。
グーグルの検索窓に知りたいことを数単語打ち込めば、答え?はネットですぐに見つかります。
例えば「つけうどん レシピ」と検索すればつけうどんを作るのに必要な材料と調理の手順まで即座にわかります。そのレシピに従えば、まずくなることはありませんし、失敗することはなくなります。
「調べれば求める答えが得られる」
そのように考えている節があります。
また、インターネットでは情報が分散しがちで、真偽もわかりにくいところがあります。そこで、 信頼性とまとまりのあるソースとしての本が登場するわけです。
「最適解をすぐに求める自分の性格」x「もともとの本好きの性格」=わかんなくなったらすぐに本!
という方程式が成り立っていました。
なぜ本をすぐに探すと違和感があるのか
すぐに答えだけを見つけようとする。これを考えた時に、中高生の時の数学の授業を思い出しました。数学の授業があまりにもわからなかった私は、課題が出るたびに問題集の答えをみて、それを書き写して今いました。ただの答えの写経です。答えをみれば、解き方はわかります。むしろ一時期通った塾では、数学の問題を解く時に悩むのは愚かだ。むしろわからなければ答えを見て、解き方を知るほうが大事だ、とまで言われました。数学では答えをみることが推奨されていたと思います。
数学の問題集は答えをみればすぐに解けた気になってしまいます。しかし、その代わりに失われたものは試行錯誤と、発見の感動です。気づけば問題集をおわらせることだけが目的になってしまいました。
このように、答えをすぐに求める性格に、高校の勉強から大きな影響があったように改めて思います。
しかし、数学の問題は解く方法がたくさんある場合があります。解き方はほんとうにたくさんあるのです。それを自分で発見し、答えがあっていた時の感動は今も忘れられません。
本ですぐに答えを探す違和感は、この答えを求める過程の思考と腑に落ちた時の感動を失ってしまっているからでしょう。
答えを出さないで考えてみる
もちろん本は素晴らしいものです。自分もずっと読み続けてきたので、本を否定するつもりはありません。ただ本を読むことで考える時間を失っていては本末転倒だと考えるようになったのです。
まず考える時は自分の頭で考えてみる。本やインターネットの情報は参照するのには良いですが、きっと「答え」ではないだと思います。 なぜならその本に書いてあることは、あくまでも著者のものだからです。