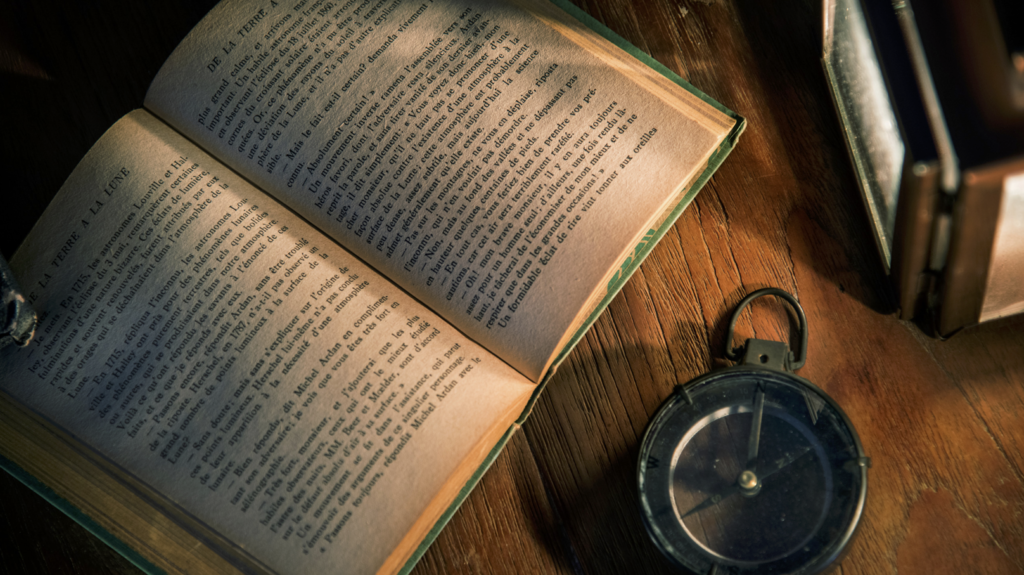2021年1月の読書
読んだ本の数:7冊
読んだページ数:1606ページ
■スマホ脳(新潮新書)
私はスマホ依存症だなと思いながら、なかなかやめられませんでした。
この本を読んでスマホ依存の怖さを再認識。巻末の具体的なアドバイスのおかげで2時間ほど1日のスマホ利用時間を減らすことができました。
他にもまだ試していない方法があるので、今後もスマホに依存しない工夫を試していきたいと思っています。
■人生は楽しいかい?
自己啓発本だと思っていたけれど、それだけじゃなくて身体のことをしっかりと取り扱っていてとても参考になりました。
物語形式でキャラクターもユニークで読みやすかったです。
「システマ」というロシアの武術を通して、身体から人生全体まで幅広く網羅しています。
こちらはAmazonのAudibleで耳で聴くことができます。私は散歩をしながら毎朝聞いていました。通勤途中に電車の中で聞くこともできます。

■死を生きた人びと――訪問診療医と355人の患者
なんとなく自分がどうしたら、悔いの無い人生を送れるかばかりを考えていたのですが、日本の医療体制や金銭の問題など、社会的に望んだ死を選べないシステムがあることを学びました。
まだ一読目だけれど、もっと深堀していきたいと思います。
■大河の一滴 (幻冬舎文庫)
何回も読み直すと思う1冊。
昔の本だけど今なお切実な言葉の数々。
■最強の集中力 本当にやりたいことに没頭する技術
「2時間の映画を長いと感じる」
「本1冊を一気に読み切る集中力がなくなった」
自分の失われた集中力を取り戻すために何をすべきなのか、今まで読んだ集中力系の本の全ての知識が網羅されている本でした。
■在野研究ビギナーズ――勝手にはじめる研究生活
2021年は今までと違って一つの本を深堀して行きたいと思っていました。
自分の常々勉強していることは、卒業論文の延長です。
そこで自分で研究する姿勢を学べればと考えて購入しました。
複数の研究者さんの事例が紹介されており、それぞれの研究スタイルが4種類に分類されています。
自分にあった研究スタイルを考える上で非常に参考になりました。
■チッソは私であった: 水俣病の思想 (河出文庫)
昨年から天草や水俣について勉強するようになり、その流れでこちらの本に出会いました。
日本の自然の豊かさ、そしてそれが失われつつあること。
東京にいるとお魚やお肉が商品としてスーパーに並んでいます。
そうすると生命の命を奪っているという実感がありません。
先ほどご紹介した「大河の一滴」でも書かれていましたが、生命の実感から離れたことが現代の様々な問題につながっているのではと常々感じています。