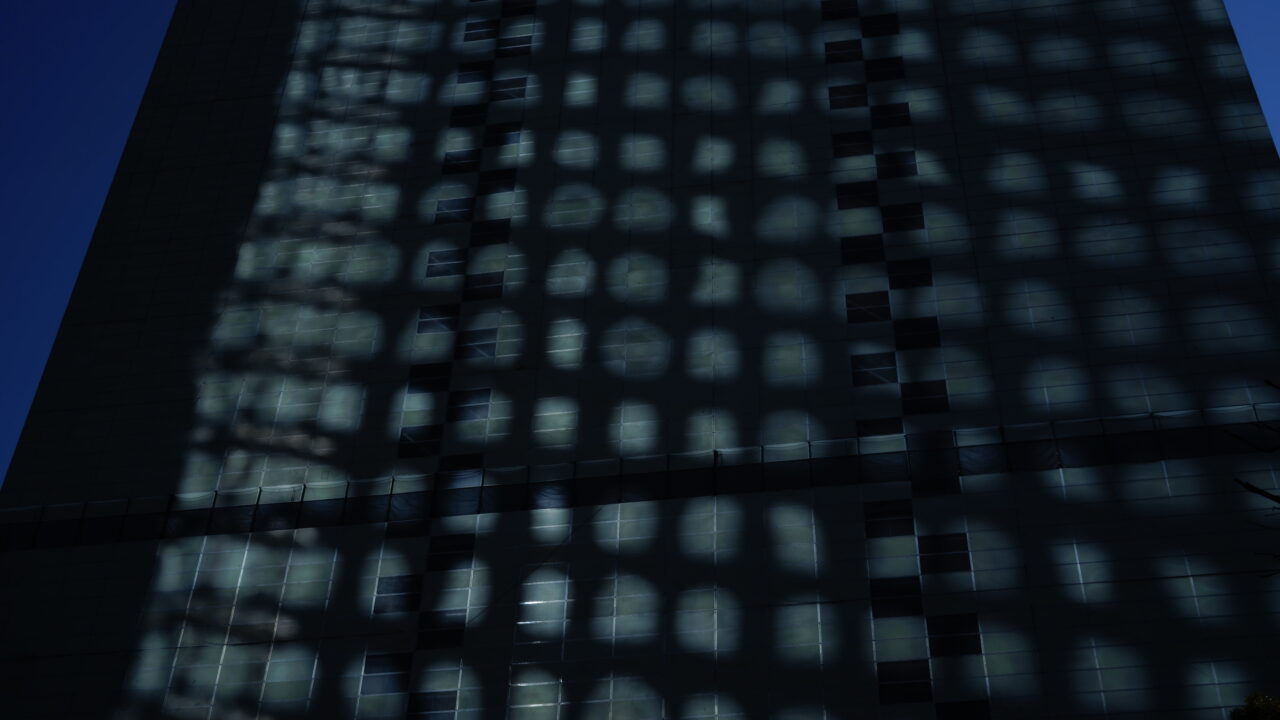昨年2022年12月16日、『生成と消滅の精神史 終わらない心を生きる』を刊行されたばかりの下西風澄氏(https://twitter.com/kazeto )をゲストにお迎えした松葉舎ゼミ第2回(https://www.shingoemoto.com/seminar/ )に参加してきました。
冒頭では松葉舎代表の江本氏(https://twitter.com/shingoemoto )が書籍について講演を行い、筆者の下西氏が補足をいれるという形になりました。以下、僕が参加して感じたことや理解したことをメモしておきたいと思います。
生きづらさのもとを辿る、心はどこからきたのか
まず私たちは現代社会に生きていると息苦しさや辛さを覚えたことはあると思います。心の病気と呼ばれるうつ病に関しては100人いたら6人はうつ病だと言われるほどひろまっています。小学校の学年に1、2人はいるくらいの規模感です(参照:https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_depressive.html )。
ただ自分の心がつらいと感じていても、そもそも「心」とはなんなのかを考えることはありません。人々が生きづらい社会において心がどこからきたのか、心とはなんなのかを考えることは大きな意味を持ちます。
本書はまさに心の来歴、あり方の変遷について語った本です。下西氏は紀元前5世紀ごろに「心が発明された」時期にまで遡ります。
心は「発明」された
まず古代ギリシアにおいてソクラテスによって心が発明されました。古代ギリシアのころは、日本は縄文時代あたりになります。本書ではソクラテスが魂をエピメレイア(管理)せよ、といったことで心は神から分離されたと語られるわけですが、そもそも心が発明される以前の人類はどのような精神性を持ち合わせていたのでしょうか?
そのヒントになるのが「イリアス」だといいます。「イリアス」の中でアキレウスが怒りから剣を抜こうとする場面があるのですが、アテネという神様の登場によって怒りは突然収まります。神の意思が間に入ることで、人の行動が変化するわけです。
神の意思が行動に影響する、それは言葉の語源をたどってみるとよくわかります。
英語の”soul”,”mind”の語源は、ギリシア語でpsycheになります。この原義は風、呼吸です。
自分一人が行動に影響を与えているわけではなく、神の意思が風にのって運ばれてきて、呼吸によって体内を巡ります。だからアテネの登場でアキレウスが突如行動を変容させたように、私一人の意思だけで行動しているとは思われていませんでした。
そうした中、ソクラテスが神と心を分離したことにより、人は心の自由を手に入れると同時に、決断の苦悩や責任の重み、心の葛藤に苛まれることになっていきます。
キリスト教の登場:アリストテレスの再発見まで
キリスト教が登場したことでソクラテスの思想が忘れられていきました。ソクラテスの心は重すぎたわけです。神から分離した心の重みに耐えかねて、それをキリスト教という新しい神に再び委ねていく。ただ、そのキリスト教の神も、気候変動に伴うライフスタイルの多様化によってキリスト教は人々の生活を統御していく力を失い始めた。そこに宗教改革だったり科学革命だったりが生じてキリスト教の権威が損なわれていき、再びひとびとは自らの心を自分で支えていく必要に迫られた。彼らの智はアラビアの方で保管され、レコンキスタによって13世紀ごろから15世紀ごろに再発見されます。
デカルト:全世界の存在責任を心に背負わせる
「我思う、故に我あり」
この言葉は多くの人が聞いたことがあると思います。筆者も高校の倫理の時間に習いました。この言葉の生まれた背景には全てを疑い続けたデカルトがたどり着いた、全てを疑う私自身は疑いえないという考えがあります。そのようにして確保した、唯一確かなものとしての「疑う自分自身」を基盤に世界が再構築されており、私の心が世界存在全てを背負います。この責任はあまりにも重い。
パスカル:宇宙と対峙した小さな存在
続いてパスカルは「人間は考える葦である」という言葉を残しています。人間は葦のように弱い存在であるが、それは「考える」葦である。考えることによってパスカルは宇宙をおのれの心のうちに包みかえそうとした。宇宙と対峙する小さな存在として弱い人間を置いたわけですが、それでも僕ら人間に課せられた責任はあまりにも重い。この責任を軽くしたのがカントです。
カントのフィルター:それはあまりにも冷たいAI
カントは心の仕組みに目を向けました。人はあるがままの世界(モノ自体)には触れられないという気づきから、心が世界を見る際のフィルターになっていると考えます。心を通して私たちは世界を見ているわけです。
これは心がいかにして世界から情報を取得しているか、という話になってくるわけですが、ここにある疑問が生じました。心とはただのフィルターに過ぎないというのは、世界の責任を負わされることは無くなったわけですが、あまりにも冷たいのではないか?というものです。
それこそただのフィルターでしかないのならAIのようなものでも構わない。そこから人工知
能の話に飛躍してしまいますが、まあ脳がPCみたいなものだと考えていくような考えもあったわけです。そこに異論を呈したのがフランシスコ・ヴァレラという人でした。
フランシスコ・ヴァレラの生命観:世界との間で遊ぶ心
生命とは自律的な運動によって自己とその他を区別するシステムだと考えたヴァレラは、自身とその他を区別する境界線が常に更新され、揺れ動いていると考えます。カントが心をフィルターにして世界を見ると考えたのに対して、ヴァレラは世界と自分の関係を動きながら構築していくわけです。
古代日本人の意識を考える:柿本人麻呂が波飛沫に見た心
さてここから話は少し変わります。西欧での心の変遷を見てきたわけですが、日本はどうだったのでしょうか?
筆者は柿本人麻呂のうたから話を始めます。「石見の海打歌の山の木の間より我が振る袖を妹見つらむか」といううたで、柿本人麻呂は岩に当たる波飛沫に涙をみてとります。心と自然が混じっていた。
いまだ引き継がれている夏目漱石の苦悩
明治になると日本には西洋の心が強制的にインストールされます。古代ギリシア人のように、自然から心が分離したことの苦しみを感じ始めるわけです。それを如実に表現していたのが夏目漱石でした。母なる自然に還りたいと思いながらも、それだけではいけない。自然からきりはなされた心を委ねうるものとして技術を見出しますが、技術、機械に心をすべて譲り渡すわけにはいきません。
筆者は、現代人はいまだに漱石の苦悩を解決できていないと言います。
柿本人麻呂の時代から私たちに引き継がれてきた歴史的身体感覚と、西洋からインストールされた自我が一致していません。
心の旅は終わらない:生成と消滅の物語
ここまで古代ギリシアからデカルト、パスカル、カント、ヴァレラ、そして古代日本人の心から夏目漱石の苦悩まで見てきました。
ChatGPTの登場によりもはやもう一人の万能アシスタントとしてAIが台頭してます。イラストもコマンドを入力すればAIが美麗イラストを描いてくれます。アニメーションや動画など人にしかできないと思われてたものがあり得ない速度でAIができるようになっています。こうした状況のなかで、私たちは「心」をどう捉えなおしていくべきか。
この本では「あるべき心」の方向性は示されてはいません。そこには、あるべき心をひとつに定めるようとすることから心の苦悩が生まれるという考えがあります。これまで心のモデルは生成され、消滅してきており、心の旅は終わらない。
さいごに
ということでここまで昨年末に開催された松葉舎のイベントの内容を自分なりにまとめてみました。おそらく不正確な点や、説明の至らない点もあったかと思います。ただ息苦しいと感じる現代社会を生きている私たちにとって、心はフラジャイルなものであると考えることは大きな助けになるかもしれません。そして情報、技術が加速度的に発達していく時代において、心のあり方を再度考え直していく必要があります。もし関心を持たれた方がいらっしゃいましたら、ぜひ書籍の方をご覧ください。