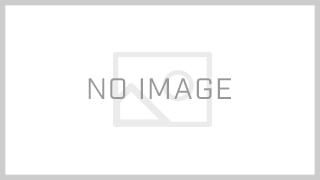最初の数ページを読んで、色々と考えることがあり、今回は「旅」について改めて考えたいと思いました。
最近自分の旅について違和感を感じるようになっていました。
フランスやイギリス、イタリアを旅していてもいつも
「なんか似ている」
という感覚がつきまといました。
どこにいても英語が通じて、英語の標識があります。
たまには日本語も通じます。
観光地に行けばたくさんの観光客と、それを目当てにしたお土産屋で溢れています。
花の都パリに行って観光して、帰ってくる。
エッフェル塔、凱旋門、ルーブル美術館、モネの「睡蓮」。
憧れの街を巡って帰ってくるのは最高の経験です。
しかし、なんか違うなという感じが最近していました。
そしてそれは、有名な都市を訪れる度にその感覚は募っていきました。
友人と話をしてもその話になりました。
「なんか都市飽きたし、郊外とか、マイナーな国が楽しそうじゃない?」と。
なんでこのような風に感じるのかな、と気がかりではありました。
高城剛さんのオーガニック革命 (集英社新書)を読んでいて、
彼は「リアルに関わること」を大切にしているとわかりました。
彼は世界を旅しながら、現地の人々のリアルに触れることを大切にしていたのです。
そこでハッとしました。
我々の旅は確かにリアルな旅ではあるけれど、現地の人と関わったり、文化に深く触れることができていないのです、
つまり、大事なのは「深度」なのです。
最近の旅は旅をしてもその土地との関わりの深度が浅い。
旅のガイドブックをみて、その言うとおりに従い、有名どころが間違いない場所として人気になる。
インターネットで世界中の情報が手に入れられるようになり、食べログや地球の歩き方に乗ってる場所は間違いないし、問題もありません。
そしてそういう場所に人は集まります。人が集まると、さらに口コミなどで有名になり、さらに人が集まっていく。
インターネット時代にローカルは埋もれていき、外向きの店、場所がその街の顔になっていきます。そこで街を感じた気になります。
しかし観光客が集まる場所をローカルは避けがちになるのも事実です。
やはり、観光客が集まるところからは、その土地の土着性、ローカル性が薄まっていきます。
その土地のリアルに触れるには、ネットにない情報を参考に、現地で人と関わって手に入れた情報だったり、現地で自分の直感に従って店を選んで冒険してみたり。そういった努力が必要なのかもしれません。
先日ウクライナに行ってきました。
ウクライナは英語があまり通じず、文字もキリル文字です。全く馴染みがない言語環境に置かれ、しかも便利な英語も使えない。
これは困りました。しかし同時にこの不便さの中で、「旅してる!」と感じたのも事実です。
観光地が便利になる中、まだザ・観光地になっていないウクライナは楽しかったです。
とはいえウクライナも観光地化し始めていて、たまに英語表記もあったしいい方でした。もっと郊外に行けばさらに大変だったでしょう。
でもそれが、その不便さこそ旅なのでは、と思います。
それこそが、現地の人と深く関わることだと。
確かに旅は不安です。
何か危ない目にあったりしないかこわいです。
だからこそ安全を求めて地球の歩き方や有名なサイトを参考にする。
一方で、そういう情報なしに現地と深く関わる旅がしたい。
最近はそう思うようになりました。
ウクライナの旅の様子はこちら