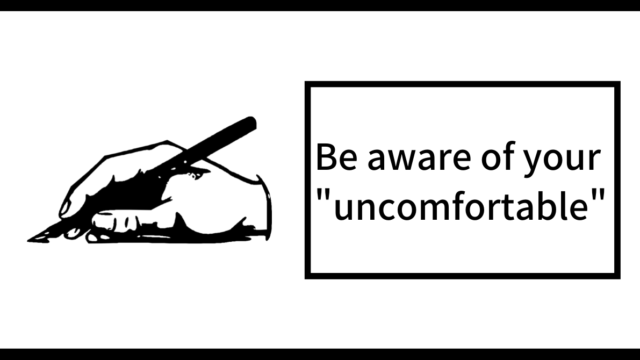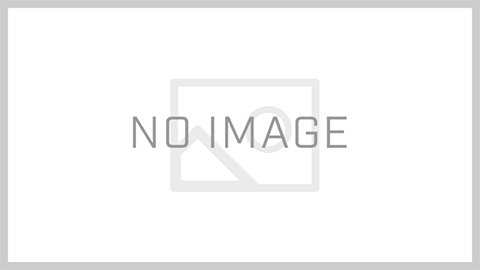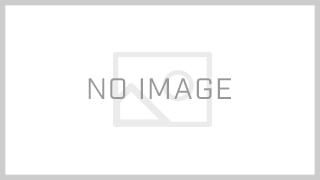こんにちは。シンイチです。
最近『陰翳礼讃』谷崎潤一郎を読んでいます。
この本は忘れられた日本人の翳の文化を語っていて、
特にヨーロッパと比較した日本人のもつ「暗闇」的な文化の記述にはひどく納得しました。
例えば、昔作られた螺鈿や金塗りの装飾が施された品々は「闇」の中で見る為に作られてる、と。
確かに、美術館で見るとき、いつも派手で面白みがない装飾だなあ、と感じていました。照明に当てられ、隠れる部分がないほど赤裸々に展示されているのですから。
しかし、あれらの作品は「暗闇の中で鑑賞するものであった」と筆者は主張します。
想像して見てください。
黒塗りの箱に螺鈿細工の施された箱があります。
それを暗闇の中で見たとき、
その螺鈿のかすかなきらめきはさぞ美しいことでしょう。
暗闇の中に妖しく光る色合いの美しいことでしょう。
他にも様々な例を挙げて、日本の文化がいかに「翳」のなかにあったかを語ります。
しかし、現代日本は暗闇を忘れてしまってはいないでしょうか。
街中には明かりが溢れ、特に東京は暗くなるということを知りません。
スマホ、電燈、街灯り。光に晒される毎日です。
この漫画に次のように書いてありました。
「人間は灯りを発明した……」
「それによって人間は闇への恐怖も克服した」
「だがそう思っているだけで実のところは……」
「闇をいっそう濃くしてしまっただけだ」
闇への恐怖は凄まじいものがあります。
先日青森の弘前の近くの旅館に留まっていました。
あたり一面田んぼで、街灯もあまりない道を散歩していた時に、
横にこんもりとした森が見えました。
その森に行こうと足を向けたのですが、そこから一歩も動けませんでした。
暗闇の中にいっそう暗闇をたたえる森に恐怖を感じたのです。
「暗闇に対する恐怖」というものを久々に感じました。
しかし暗闇に対する恐怖とは、僕らは近くにあるべきだとも感じています。
そしてそれは恐怖だけでもないと思うのです。
先日北海道で地震があり、大規模な停電が起こりました。
その時、twitterで夜空の写真がたくさん掲載されたのをご存知でしょうか?
街の光がなければあそこまで綺麗な星が見えるのか、
と感動さえしました。
都会で暮らしていると忘れてしまいそうな「翳」と共にあること。
それを思い出したい、そして忘れずに暮らしていきたいと思いました。
最後に『逆光』トマス・ピンチョンの巻頭に掲載された言葉を紹介します。
世界はいつだって夜さ。じゃなきゃ光なんていらないさ