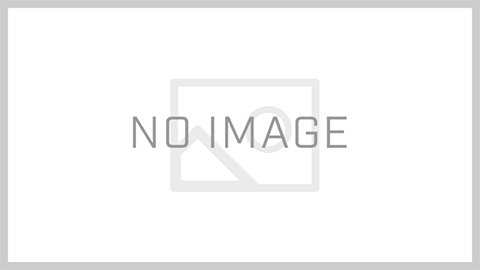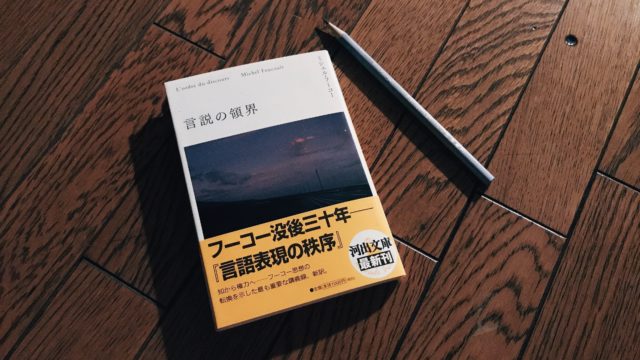帰り道に、どこかの家から美味しそうなご飯の匂いがする。
きっと誰かが料理をしている。誰かのために。自分のために。
何かの炒めだろうか。にんにくと醤油のいい匂いだった。
匂いがした瞬間、何か懐かしいような気持ちになると同時に、誰かの家が近くにあるという当たり前の事実に気がついた。
自分が今家に向かっているように、誰かにとっての寝泊まりする家がある。
それも東京を眺めた時に、周りの窓明かりの一つ一つに誰かの生活がある。
世界は多面的なのだと思い至った。
自分は自分が見ている世界しか見ることが出来ない。自分のこの目が見つめるものが、私に見えている世界だ。
でも、たとえあなたの目の前にいる人でも、あなたと同じ世界にはいない。
横に並んでも少しズレた世界を見ることになる。
人は同じものを見ていると前提して、話を進めるけれど、同じものが見えているなんてほとんどありえないことだ。
僕にとって緑色だと思うものが、もしかしたら隣の人にとっては「みどり」と呼んでいても、違う色を認識しているかもしれない。
世界は多面的で、僕がみている世界と同じものを見ている人は1人としていないことになる。
昔読んでた漫画で、相手の視界に侵入するスキルを持った主人公がいたけれど、彼くらいになれば同じ世界を見れるかもしれない。
でもきっと、視界が一緒でも、その世界をどう感じるかが違う。
これだけ一人ひとりが豊かに物事を見ているのに、それを表す言葉は限定的だ。言葉にする時にこぼれ落ちる自分の感覚というものがあって、そういう共通部分で人は会話している。
中島敦の「文字禍」という短編が好きだ。大学受験の時に、過去問で出てきた。その試験の問題と回答があまりにも馬鹿馬鹿しくて、僕の高校の先生も、こんな回答間違ってると言っていたから変に印象に残った。そして、文章自体も好きだったので、この話をプリントアウトして毎日持ち歩いては、たまに読んでいた。
文字の霊性みたいなものについて語られているけど、僕はそれがあると思っている。
文字を書く時に物凄く顔をテーブルに近ずけて書く。これは小学生の時からの癖で、鼻の頭がテーブルについてしまうくらいの距離で文字を書いていた。
中学生くらいの時に姿勢が悪いと知り、それからなるべく頭をテーブルから話そうと意識している。
これこれ15年くらいその努力を続けているが、たまに元に戻ってしまう。特に戻るのが、絵を書いているときだ。
絵を描く時にその1本1本の線をしっかりと見ようと目を近ずけてしまう。
これは先日気づいたのだけれど、姿勢よく頭をテーブルから離して文字を書くと、文字は意味を伝えるもの、くらいにしか思えない。
でも、鼻をテーブルに付けるようにしてみると、その文字がただの文字ではなく、ある1種のキャラクターというか、物語を持っているように見える。
子供の頃にテーブルに顔をギリギリまで近ずけていたのは、文字の霊性を見ようとしていたのかもしれない。
文字の霊性がなんなのかわからないけど、何か意味を伝える以上の何かがある感じはする。
書道で文字を書いていると、その文字が意味をなさずに一種のイラストとか、意味が崩壊するような経験もする。
自分が何を見ているかとか、言葉や文字がどういうものなのか。改めて考えてみると意外と分からなくて、それが面白い。