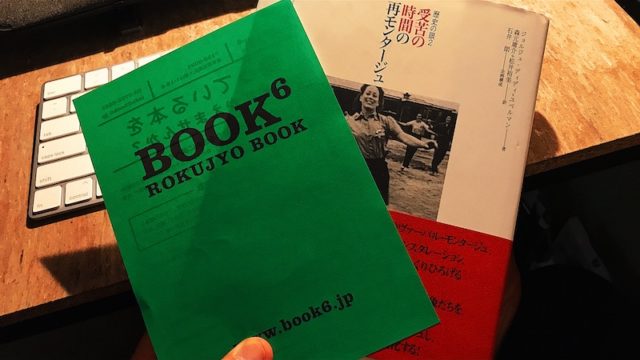昨日はワタリウム美術館で行われる、鈴木大拙の連続講演に参加してきた。第一回は安藤礼二氏の講演で、途方も無い情報量で大拙とアート、音楽、宗教の関係性が語られた。公演が終わっても頭が追いつかずにオーバーヒートしてしまい、ボーッとしたままその日をおえた。ブログを書こうにも頭が動かなかったのが本当のところである。
翌日になっても頭が講演のことでいっぱいだった。日課で本を読もうと思ってもまったく頭に入ってこない。というよりもむしろ面白かったはずの本が全く面白くない。物足りない。
その物足りなさは熱量が足りていないことへの不満足だった。
どうして昨日の講演があれほどエキサイティングで、今日の読書がつまらないのか。
<リアルと読書の差>をそこに感じた。
講演会はリアルである
講演会はリアルだ。その人が目の前にいる。2時間という限られた時間の中で登壇者自身の手によって凝縮された情報が伝達される。
<有限にすることが大事>だと「勉強の哲学」の中に書いてあったが、まさにその有限化された知識がものすごい密度で展開されるのが講演会である。
読書はリアルか?
講演会に比べると、著者が少し遠いと感じてしまう。一方で、自分のすきなように知識を習得していけるのが読書のいいところだ。何時間かけて読んでもいいし、わからなければ繰り返し読むことができる。また時間を超えて自分の成長を実感できるのも読書のいいところだ。須賀敦子さんも「塩一トンの読書」でそのように書いていた。
どちらにも良い点はあるが<有限>であるという点で講演会のほうがいいのかもしれない。確かに、本で何度も何度も念入りに調べるのもいいが、2時間だけと決めて集中して、話を本人から聞くほうがより濃い体験ができると思うのだ。