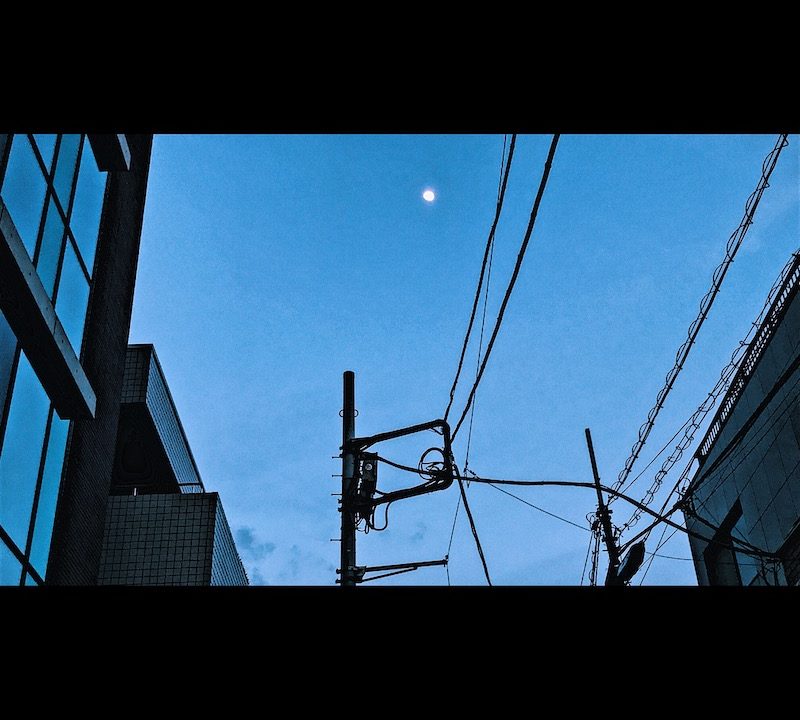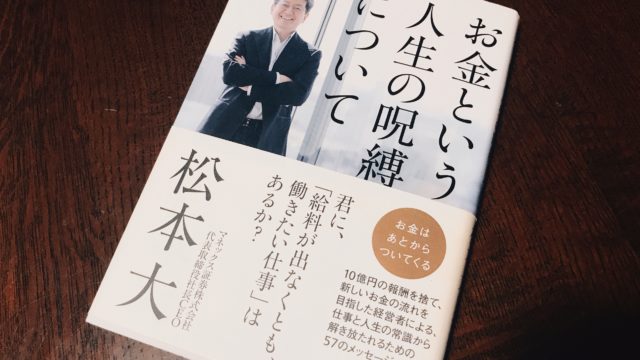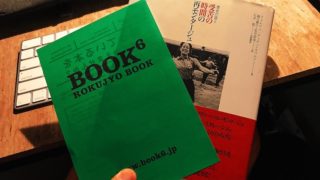自分が最近勉強をしている中で、「哲学マップ」という本の勉強をしているということを以前にも記事に書きました。
哲学マップというのは貫成人さんが書かれた本で、哲学のヨーロッパにおける歴史を新書のサイズで概観するという素晴らしい本の一つです。この本を読みながら哲学というのはありとあらゆる思索するという行為に関わってくるため、自分の興味関心を「哲学マップ」で考えてみるという勉強をしました。
哲学マップで自分の専門としているホロコースト・ユダヤ人問題について、年表を作っみました。
哲学、ユダヤ問題、世界史マップ
哲学者の生年月日、活躍した時代とユダヤ人問題の歴史、そして世界史の年表の三つを組み合わせて書いてみました。年表を書いてみると、哲学マップでは中世の部分が抜けていたり、哲学マップで最初に出てくる哲学者タレスは紀元前600年頃なのですけれども、ユダヤ教の歴史はもっと前紀元前1500年などからあるということがわかりました。
マップを作って気づいた3つのポイント
このように年表でユダヤ人問題と世界史哲学者の歴史を眺めていく中で気づいたことが三点あります。
- 一つ目は限定哲学の中でユダヤ人哲学者がとても多いということ
- 二つ目はユダヤの歴史の中で18世紀頃に法律で人権が認められるまでは本当に差別の歴史が長かったということ、またその人権が認められたと言っても二十世紀にドイツの法律でまた差別の歴史が始まってしまったということ
- 三つ目が、ホロコーストを経験したことで数多くいる哲学者の思想がどのように変わったのか
18世紀頃の人権の改善というところには、フランス革命が大きく影響しています、フランス革命は王制から国民主権へと舵を切る大きな出来事で、全ての人民に平等に権利を与えるという名の下でユダヤ人にも人権が与えられたとされています。
とはいえ、実際にどうだったかというと話しは別で、法律が決まっても決して実情としては差別は改善されたとは言えなかったというのが現実のようです。とはいえ、法律的に改善されたり、イギリスで公職に就く事がオッケーになったりなどある程度の改善が見られた時代だったとは言うことができると思います。
また、ユダヤ人哲学者が多いということ、ユダヤ人哲学者がホロコースト以前と以後どのように思考を変えたのかというのは非常に大きな問題だと思っています。一般的にいうユダヤ人は頭がいいと言われるようなところがあって、ノーベル賞の受賞者などは本当に数が多いです。哲学に関しては、彼らがユダヤ人であることが、自意識や存在などについて多く関連していると思われます。
次にホロコースト以前と以後でどのように思想が変わるかという話ですが、これに関しては様々な哲学者の文献を読まなければなりません。
大きく概観するマップを作ると、細部に気づける
マップを作ると様々な事象を大きく概観することができます。それこそホロコーストの差別を撤回するような法律が制定されたという一部を見てみても、本当に撤回されたのか、実状はどうなのか、どのような背景でその法律が制定されたのかなどを考えると、1行1行を細かい部分を見れば切りがありません。
そうすることで大きなマップを作ることで、また新たなデティールに目が向くという経験をしました。1度大きな枠組みを知っておき、その中からまた小さい部分にフォーカスしていくという手段は他の勉強でも有効だなという風に感じます。
確かに高校受験の時、世界史を勉強する時も流れを知ってから細かい年号などを暗記していく方がいいという風に先生に教わり、そのように勉強した記憶があります。
また、大きな流れで見てみると、今まで自分はホロコーストについて勉強していたのですが、これはただ20世紀の、本当に一世紀の出来事を詳しく見ていただけで、それ以前の歴史となる何千年も前まで遡れることが分かりました。そこまで考えてやっと19世紀20世紀の差別についても分かってくるのかなという新たな見方も発見することができました。
なので大きく概観するというのは本当にいい手法だという風に思っています。1度マップを作ると、そのマップにさらに重ねて、他の事象を重ねることができると思います。例えば自分が腸内細菌や病原菌に興味があるので、そういうものの発見の歴史を重ねることができます。例えば、ペストなんかはユダヤ人が原因とされ、ユダヤ人が大量虐殺されたという歴史もあります。一つの大きな流れを1度作ってしまえばそこに重ねていくことができるという意味でも大きなマップを作ることをオススメです。では。