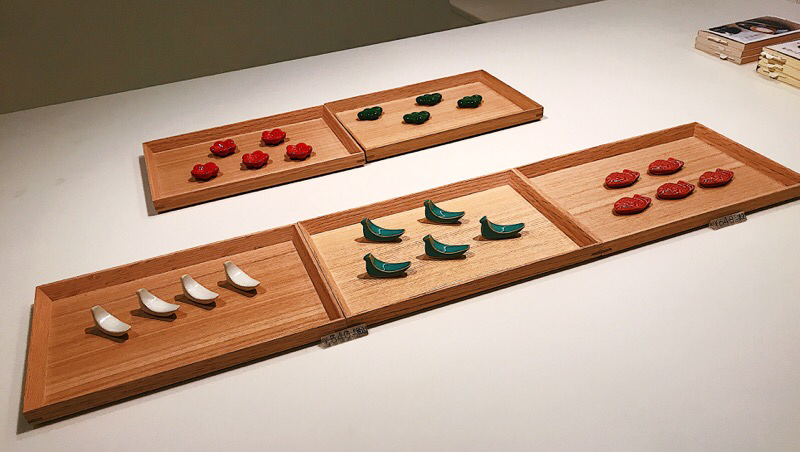1954年版の最初の「ゴジラ」を見ました。
Amazonプライム・ビデオで過去のゴジラ作品が全て見る事ができるようになっているので、まだ見ていない方は是非!
ちなみにこの記事では「ネタバレ」を含んでおりますので、これから見る方はご注意ください。
1953年版という事でCG技術もないので全てジオラマで撮影されています。
ゴジラは着ぐるみであり、中に人が入っています。このゴジラの動きは非常に難しかったようで、いかに人間ぽい動きをださないかで非常に試行錯誤がなされているそうです。
この映画は戦後が舞台になっており、ゴジラは水爆実験の影響で登場した怪物です。徹底的に核に反対したこの映画は、戦後を切実に反映しており、今の僕にが見るにはとても重い内容でした。「シン・ゴジラ」よりも重厚な世界観に圧倒されます。
個人の死と大衆の熱狂
この映画で最も衝撃的なシーンはラストにあります。
水爆をも生き延びたゴジラを倒す事はまったくできなく、ただただ被害が増すばかりの東京。悲惨な状況を前に、ある科学者が開発した「兵器」がゴジラを倒せる可能性を秘めていました。しかし博士は原爆、水爆につぐ大量破壊兵器を表に出すことを頑なに拒みます。
資料をすべて廃棄していても、誰かが必ず悪用する。なぜなら博士の頭の中に設計図があるから。
彼がその兵器を使うには自分が死ぬ覚悟が必要でした。
彼は東京を救うために、兵器を使用する決意を固めます。自分の死とともに。
ゴジラを倒した時に博士もいっしょに死にます。
そこで如実に現れるのは
<ゴジラが倒れたときの一般大衆、メディア>と
<博士を失った人々の落差>です。
このギャップはあまりにも凄まじくて、どう説明すればいいか迷います。
ゴジラを仕留めた博士は死にました。誰よりも今後の世界の平和を考えて。
しかしメディアは博士は死んだことではなく、ゴジラが死んだことを喜んでいます。
博士が世界に悪用されないためにと覚悟を決めて死んだのにもかかわらず、「ゴジラに勝った」、「自分たちは安全だ」と喜ぶ。
その二つの世界の落差が怖かった。
二つの世界大戦においても、このような違いがあったのではないでしょうか。
戦争で勝った喜びと、その犠牲になった人々の悲しみのように。
戦の勝利には、勝利の礎になって死んだ人と、その家族がいます。
「大義のために」死んだ人がいます。
でも大義のために死ぬとはなんなのでしょうか 。
水木しげるさんの体験記でもある「総員玉砕せよ!」という漫画があります。
この作品はもっとも自分に影響を与えた本の一つです。
この漫画では祖国のために無謀に突撃していく隊員を後ろ目に、自分だけは生き延びようとする指揮官の姿が描かれます。
誰のために死ぬのでしょうか。
戦争のことを考えると、なにをどう判断すればいいのか、そもそも経験していない僕らがなにを語れるのかわからなくなります。
それでも<考える>だけでも大きな価値があると感じています。
そしてその契機を与えてくれる作品もまた同様に大変な価値があります。
初代ゴジラが最も色濃く残した戦争を、新たなゴジラを見る前に考えなくてはいけないと思いました。