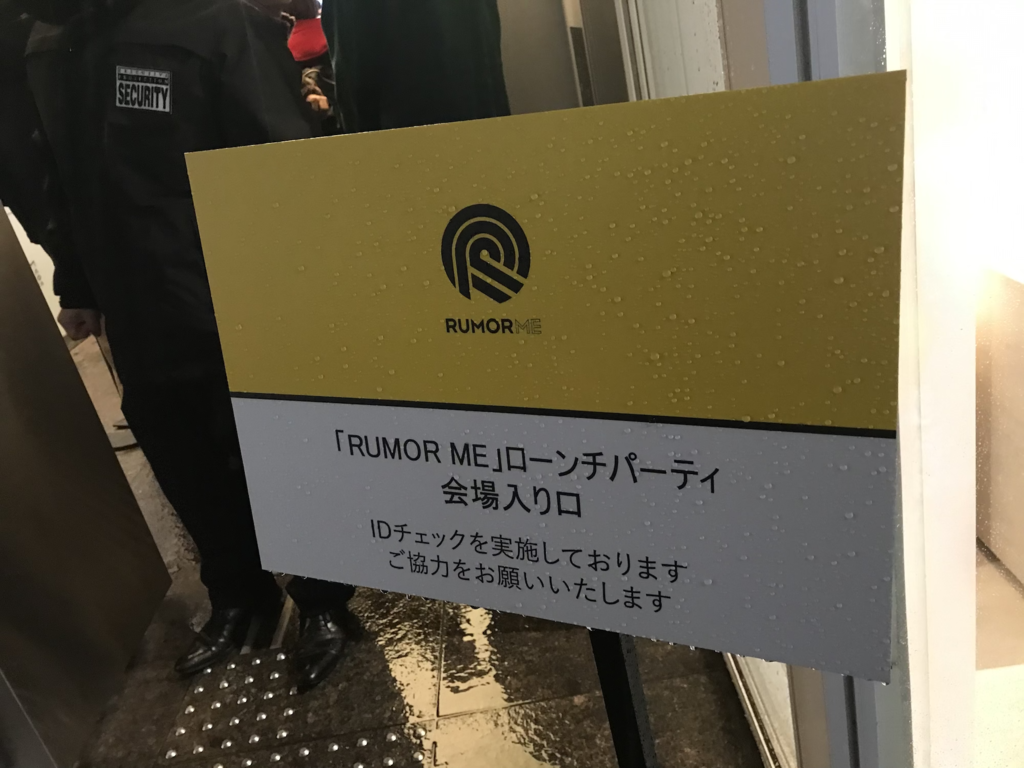今日は普段からお世話になっている私塾、松葉舎の日だった。今日は輪書という行為を3時間かけておこなった。
これは誰かが書いた文章を自分なりに書き直してみる、もしくは自分の文章を他人に書き換えてもらうという作業だ。
この一連の行為を通して、文章を書くということについて改めて考える機会となった。
自分の文書に向き合う
自分の文書の1部分を他の人に書き換えてもらう。
自分の文章と何度も何度も向き合うことがないので、いい機会になった。自分の文章の気になるところや、もっといい表現にできる、という部分に気がつける。
また、ほかの人が書き換えると、その人の息遣いやルールがなんとなく現れる。それは、書き換える態度や、書き換えられた言葉に如実に現れる。
他人の言葉で書き換えられた自分の文章を見ることで、自分の言葉の特徴に意識が向いた。私は簡潔で、ともすれば難しい言葉遣いを好むらしい。また、論理的というか、硬い文章を書いている。
書き換えられた自分の言葉を見ていると、自分の文体に気がつく一方で、言葉の可能性に意識が向く。
そうか、文章を書くというのはこんなにも自由なのか、と。「は」を「が」に変える。「例えば」を「たとえば」に変える。
大した違いはないと思うかもしれないが、読者になってみると、文章の柔らかさや読んだ感じに影響を与える。
他人の文章を書き換える
逆に自分が他人の文章を書き換えるとき、その作業には慎重さがもとめられる。
その人の言葉の意味がわからなければ、上手く書き換えることは出来ない。
自分はここを書き足したらわかりやすいな、と思うところを書き足して文書を作っていった。一方で優しい言葉遣いで説明する人もいた。
なんにせよ、まず相手の文章をしっかりと吟味しなくてはいけない。
自分は本を読む時や、記事を読む時にわりとさささっと読んでしまうタイプなので、じっくりと短い文章に向き合う体験は久しぶりだった。
そして、ゆっくりと向き合って、自分なりに書き換える作業をすることが何かまだわからないが、大切なことなように思える。