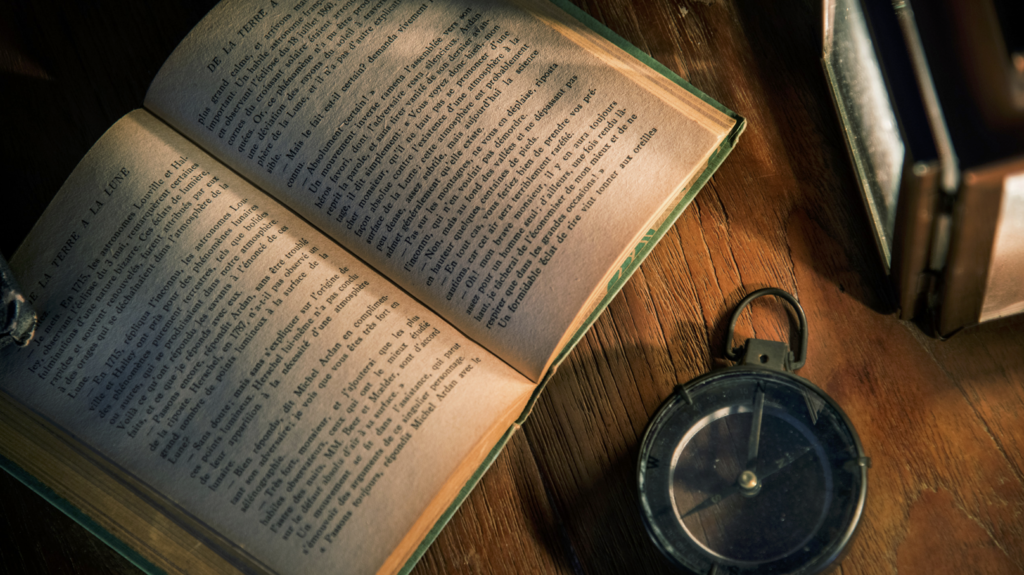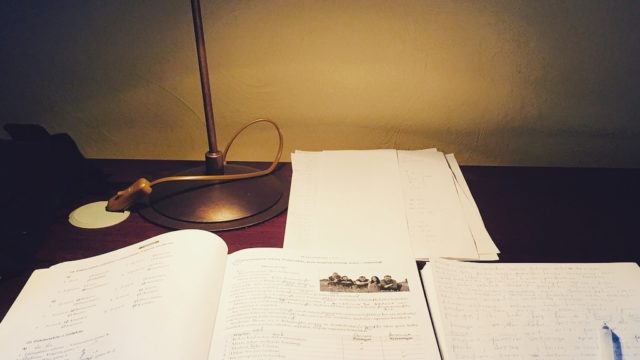みなさん、こんにちは。しんいちです。

年始の記事で2019年の目標を書きました。
この中で、「本を150冊読む」という目標を立てました。
みなさんもきっと新年の目標を立てたと思います。
その中でも「今年は〇〇冊の本を読む!」と決めた方も多いでしょう。
僕はまだ年間150冊目標を捨てたわけではありませんが、ちょっと違和感を感じました。それは…
本は読み終わっても読了じゃない
ということです。
今日はそのお話をしたいと思います。
本を読むということはなにか
ここ数ヶ月で自分の「本を読むこと」への意識が変化してきました。
以前の私は
「この本読み終わった!!ハイ次!!!」
といった感じだったんですね。
でもここ数年、自分の専門性があまりないなあ、と感じていました。
好きな本を読んでいるだけ。
周りのすごい人達はなにか「テーマ」を持って、それにそって読んで、深掘りをしていました。なので話す内容も深くて面白いです。
でも私の話はなんとなく軽薄に感じられました。
聞いた話をそのまま伝えているような。
そこに自分の思考などない、かのような。
ただただ好きな本を読んでいくのもいいとおもいます。
でもやはり一つのテーマに絞って、深掘りをしていくような読み方のほうが知識が定着すると思ったのです。
例えば、「仮想通貨」について学ぼうと思ったとします。
最初に「仮想通貨」とタイトルに入った雑誌を3冊読みます。
次に「仮想通貨」「入門」とタイトルに入った書籍を3冊くらい読みます。
そうすると基礎知識がつくとともに、自分なりに興味のある分野が出てきます。
そしたらそこを新しい本やネットの知識で深掘りしていくとう感じです。
読んだだけで終わりではない
そうやってどんどん読んでいくときにやってほしいことがあります。
それは自分なりにノートをまとめておくことです。
別に紙で書かなくてもスマホのメモでもワードでもいいと思います。
何らかの形でまとめておくことが必要なのです。
これは自分が気になった部分を書き出してもいいですし、マインドマップのように構造化してもいいと思います。
これは個人的なアウトプットとして最適です。
そして最後に学んだことをブログやプレゼンなどの形で発表することです。
私は非常になまけものなので、他の人にむけてアウトプットする場がないとどんどんさぼってしまいます。これに気づいたのが最近ですが、ブログを書くことの良さを再認識しています。
インプットだけでは思いの外知識は深まりません。
人に話す、ツイートする、ブログに書く。
そういったアウトプットを経て、知識はしっかりと定着していきます。
年間何冊目標は意味があるのか?
さてここで話を最初に戻しましょう。
「年間150冊を読む」という目標についてです。
これは思ったよりも意味がない目標ではないかと考えるようになりました。
必要なのは「どれだけ本を読んで、それをアウトプットできたか」だと思うからです。
年間何冊という目標はそれでいい目標だとは思うのですが、それをただ読み流していたのでは今までと変わりません。
まとめ
・本を読んだだけでは読了ではない
・インプットはテーマを決めて一気に何冊も読む
・どんな形でもいいからアウトプットしてから「読了」