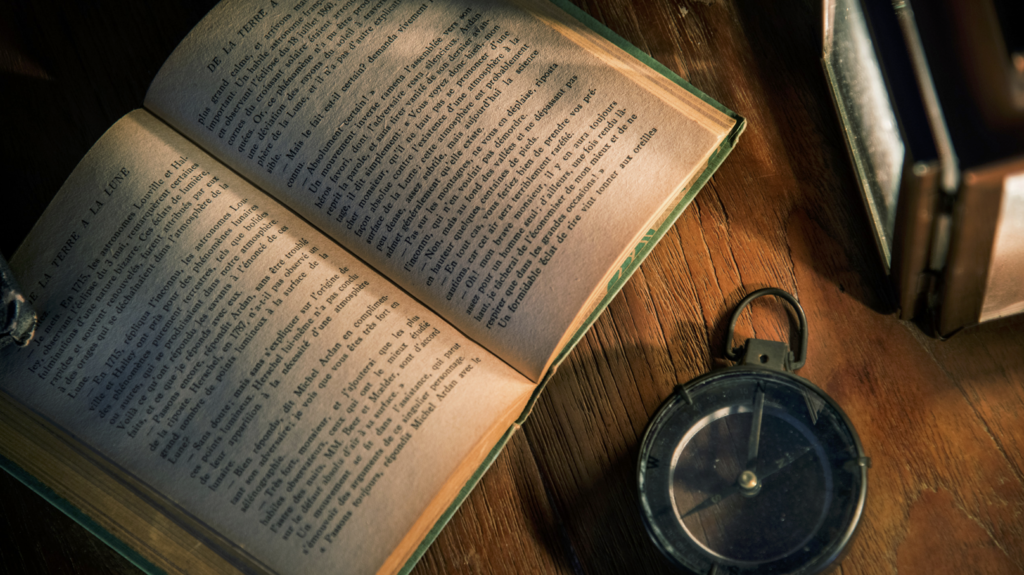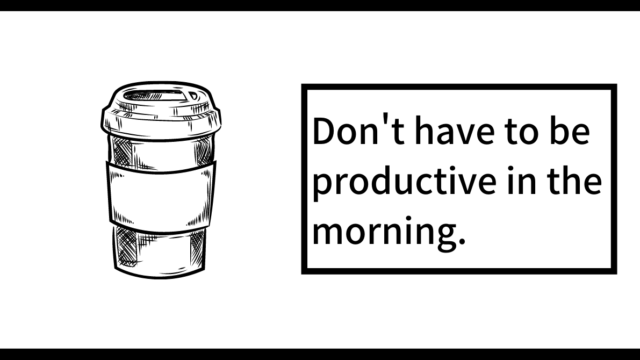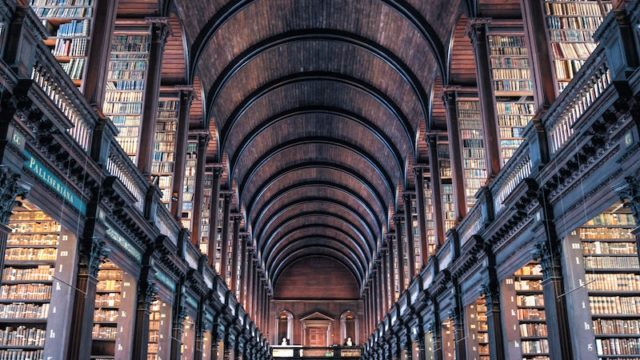今日は月に一度の書道教室の日だった。
前回の書道のときには、仕事関連で気になっていることがあった。そのことが頭を占めていたせいで、最初の方は全く良い字がかけなかった。
そして今日の書道教室では、自分の体の中のリズムがつかめると、うまくはなくても自分にとって心地のいいリズムで文字がかけることに気がついた。
今回は前回の書道で気づいたことと、今日の書道で気がついたことについてまとめてみる。
心ここにあらずの状態と書道
先程も書いたが、先月の受業では、仕事関連で気になっていることがあり、そのことが頭を占めていたせいで、最初の方は全く良い字が書けなかった。
しかし、文字を書いているうちに心の状態が穏やかになっていき、途中から文字も少しずつ書けるようになった。
このときに気がついたことが2点ある。
①頭がいっぱいだと文字がかけない
②文字を書いていると頭に余裕ができる
①頭がいっぱいだと文字がかけない
文字にその人が現れるというのは、真実だと思う。頭がもやもやしているときは、もやもやしている文字しか書けない。
文章に現れることもあるが、手書きの文字には特に現れる。
1年近くモーニングページという習慣をやっている。朝、ノート3ページ近くに思いついたことを書いていくという作業だ。
この作業は「ずっとやりたかったことを、やりなさい。」という本に出てくる手法で、なんとなく続けていた。
この本では手書きで書くことを推奨しており、それは文字にはその時の気分が現れるからだと言う。
そして筆で書く書道には、より如実に感情が影響する。
この日の前半はまったくもって文字に集中できず、いい字も書けなかった。
②文字を書いていると頭に余裕ができる
しかし、「墨をする」「筆で文字を書く」という作業を続けていくうちに、文字が少しづつ書けるようになってきた。それと同時に、頭の中も整理されてきた気がする。
確かに寝る前にその日の不安事や心配事をノートに書いてから寝ると、頭をすっきりさせて寝ることが出来ると言う。
外山滋比古さんも、日記は忘れるために書くという主旨のことをおっしゃっていたと思う。
文字を書くという行為自体が、心の中だけで考えていることを外部化してくれる。また、書道のように、悩みと関係のないことでも文字を書いているうちに頭がスッキリとしてくるという体験をした。科学的に証明された論文などがあるわけではなく、個人の体験だが。
書道のリズム
今日は特に悩み事もなく調子がよかったので、文字が最初からいいリズムで書けていた。そう、いい「リズム」なのだ。
今まであまり意識してこなかったが、書道で文字を書くときにはリズムのようなものがある。それに乗れるといい感じの字が書ける。
そしてこの「リズム」があるからこそ、体や心が整うのかもしれないなと思った。
不協和音がだんだんと一つの調和の取れた音にまとまっていくように、書道のリズムに乗ると体や心が調律される感覚だ。
心が忙しくなる時代に書道のもたらす効果を再確認した。