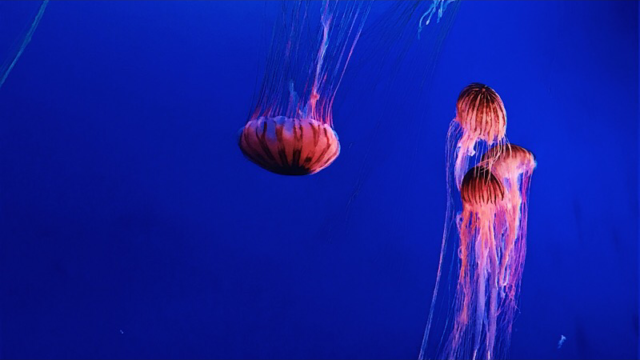今日は“LIFE IS A CARNIVAL” vol.02 “アンデスからアマゾンまで、祝祭をめぐる巡礼”に参加してきた。
世界に二人しかいないというカーニバル評論家の白根全さんと、グレートジャーニーで有名な関野吉晴さん、ミュージシャンの久保田麻琴さんという豪華なメンバーだった。
カーニバルの写真と音楽、そしてその場に居合わせたリアルな声を聞くと、今すぐにでも南米に行ってしまいたいという気持ちになる。
東南アジアを旅して戻ってきたわけだけれど、2週間ほどたった今、他の土地に行きたいという気持ちが強くなった。
東京にいると海外に行きたいのに、大変だとか、お金がかかるとか、やけに現実的なことがたくさん頭をよぎる。この海外に行く歩みを遅くさせるのは都会の何なのだろうか。これは都会に限らないかもしれないけれど。
定期的に海外への欲望を駆り立てるような出来事に遭遇しないと、どんどんと日本からでる足が重くなりそうだ。
南米のスペインに支配された歴史や、キリスト教の入ってきた記憶。土着の宗教とキリスト教の混じった神話。そしてその神話をもとに多くの人が集まるお祭りが開催されているという。
タイやベトナムでは仕事のことばかり考えていたけれど、地元の文化や宗教にもっと目を向けて学べばよかったと後悔している。
旅行に行けば行くほど、観光地を回るのに飽きたと感じることが多かった。特にヨーロッパに居たときは、協会と美術館がほとんどで、途中から少しまたこんな感じかぁ、と思っていた。
確かに「観光」では違いがわからないかもしれないが、歴史や文化的背景を知ればもっとその土地を味わうことができたかもしれない。
タイで街の至るところに王様の写真があるのはなぜなのか。それほど人気なのか。政治形態は独裁政治なのか、民主政なのか。仏教にしても日本とどう違うのか。お坊さんはなんでオレンジ色の服を着ているのか。
ちょっとしたことも本当は調べたら面白いはずだ。
次に旅するときは、歴史を学んだ上で、その土地に行ってみて感じる些細なことへの感受性を鈍らせずにいたい。
今日のトークで、また興味が湧いてきたので少し本を引っ張り出してみる。