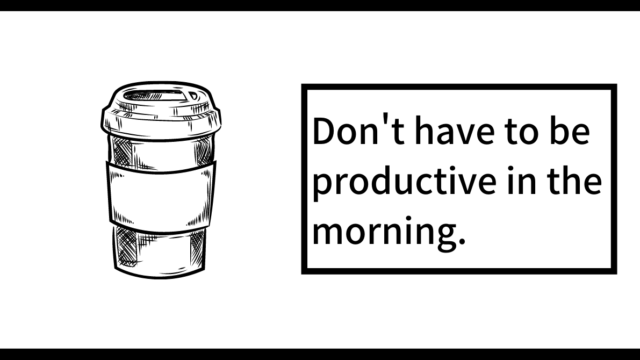物語の舞台は島原の乱が鎮圧されて間もない長崎。
島原の乱とは、島原の乱(しまばらのらん)は、江戸時代初期に起こった日本の歴史上最大規模の一揆であり、幕末以前では最後の本格的な内戦である。島原・天草の乱、島原・天草一揆とも呼ばれる。寛永14年10月25日(1637年12月11日)勃発、寛永15年2月28日(1638年4月12日)終結とされている。従来、信仰的側面は表面上のもので、あくまで厳しい収奪に反発した一揆であるというのが定説であったが、事態の推移から、単なる一揆とする見方では説明がつかず、宗教的な反乱という側面を再評価する説が出ている。鎮圧の1年半後にはポルトガル人が日本から追放され、いわゆる「鎖国」が始まった。
wikipedia
島原の乱が終結して、キリスト教への弾圧が厳しくなった長崎に、布教のためにポルトガルから3名の司祭が向かう。その中の1人であるロドリゴ神父は日本人のキリスト教信者に与えられる弾圧の凄まじさを目の当たりにする。拷問や殉教者たちのありさまを見て、キリスト教を捨てるかどうかという瀬戸際にまで立たされる。
神の存在を信じ、救いを信じている彼らが弾圧されているのに、なぜ神は救ってくれないのか。いったいどれほどの苦しみを味わえば、神が救いの手を差し伸べてくれるのか。
文庫本で300ページほどの小説だが、一度も飽きることなくページを捲り続けられる。特に物理的に緊迫するシーンや山場がドンッとあるわけではない。というか、冒頭の時点から主人公たちがどのような終わりを迎えるのかなんとなくわかっている。これは、新潮文庫の「解説」で佐伯彰一さんも書いてる。
物語が読めているのに、それでも飽きずに最後まで読めるのは、歴史的に行われた残虐な行為に耐える人々の精神や、主人公ロドリゴ神父が、日本という特殊な環境下でどのようにキリスト教に向かい合っていくのか、その内面の葛藤の描写が切実だからだ。
遠藤周作文学館に行ったとき、彼はキリスト教と日本人の間にある溝に着目して、考え続けていた作家だという主旨のことが書いてあった。彼の生涯にわたって心のなかにあった疑問の一つの到達点としてこの小説があるのは間違いない。
遠藤周作文学館は長崎駅から車で40分ほど走った場所にある。文学館が立つ場所と園周辺は、キリシタンの里として知られており、『沈黙』の舞台となった場所である。
ユネスコに世界遺産として、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が登録されており、遠藤周作文学館の周辺には
- 外海(そとめ)の出津集落(しつしゅうらく)
- 外海(そとめ)の大野集落(おおのしゅうらく)
が存在する。キリスト教が禁止されていた時代にも、密かに信仰を保ち続けた人が周辺に居たという。実際に周辺を訪れて見ると、いくつかの教会が目にとまった。
教会を訪れた日は風が強い日だった。海と険しい山に囲まれた土地で、ひどく寒い風が刺すように吹いてくる。こんな土地で、彼らはどう厳しい時代を乗り越えたのだろうか。
この土地で起きた歴史的背景のもとで、 極限の状態でキリスト教とはどうあるものなのか。1人の司教がそこでどう向き合ったのか。人間の信仰とはなんなのかについて考えさせる小説だった。
<関連記事はこちら>